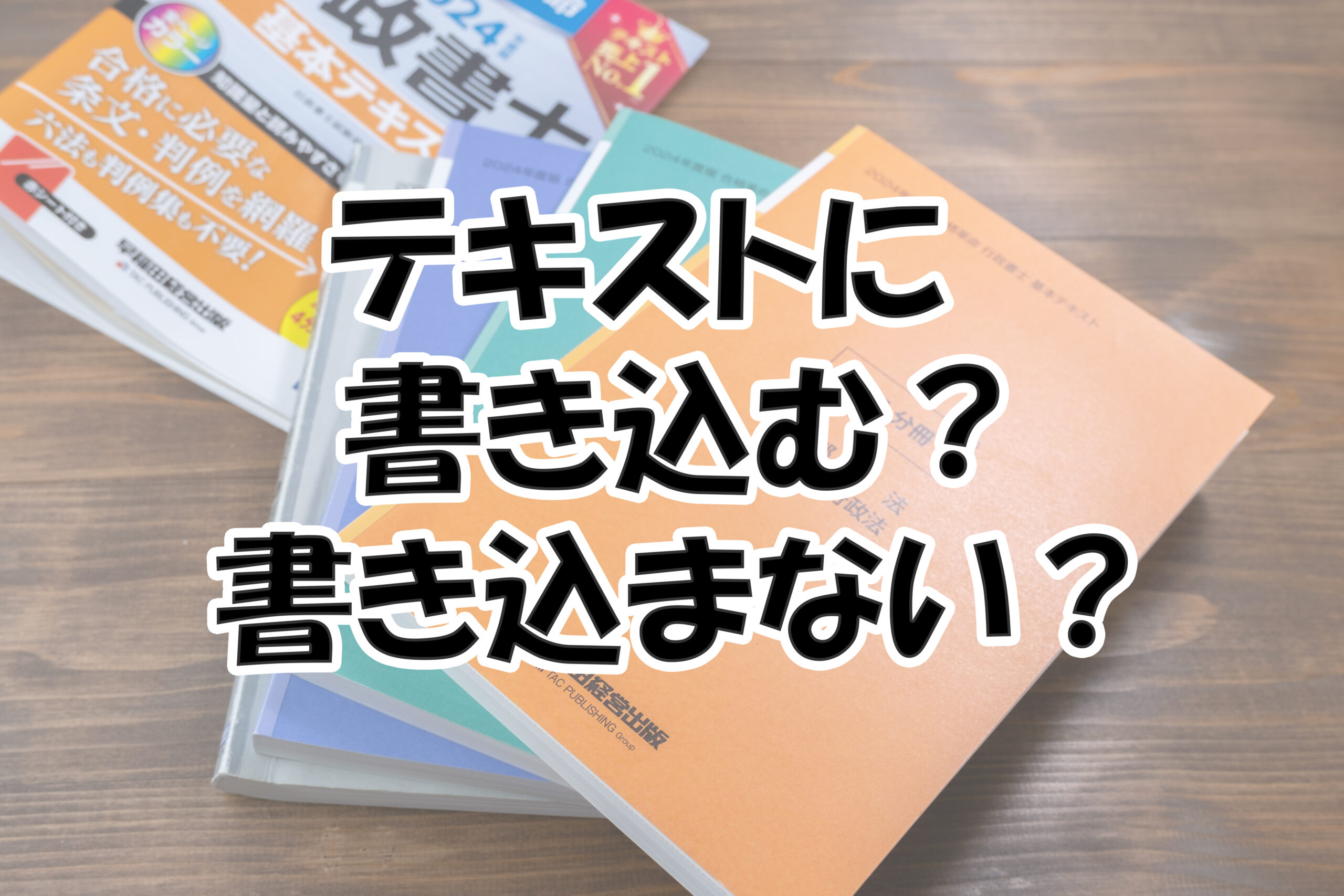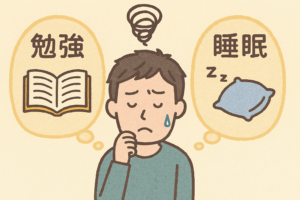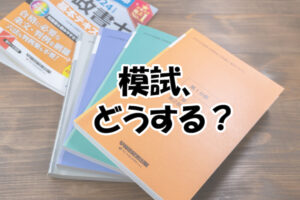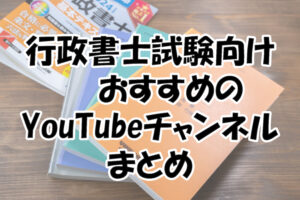こんにちは。行政書士(登録申請中)のマツモトです。
本日はテキストに書き込みは、する方が良いかしない方が良いかというテーマで書いていきます。
私は昨年(2024年)の行政書士試験において、同じ年の1月から独学で勉強を始め、独学で合格することができました。
他に、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、宅地建物取引士といった資格を保有しているため、国家資格の試験には慣れていると思います。
勉強しているうちに、テキストに書き込む書き込まない問題については、「書き込まない」という結論を得ているので、その点について解説していきます。
大前提として、テキストに書き込むスタイルの人でそれが自分のやり方として確立している人に対して、変えるべきだと主張する意図はありません。本記事はあくまで迷っている人のための記事です。
テキストに書き込むことのメリットとデメリット
結論から書いてしまいましたが、1度メリットとデメリットについて整理しようと思います。
メリット
テキストに書き込むことのメリットは、やはり情報の一元化だと思います。
特にテキストは勉強開始初期のころこそ最初から最後まで読んだりもしますが、中盤以降は確認したい事項があるときだけ開くという使い方が多いはずです。
となれば、何か気になることをテキストで調べたいときに、注意点などを書き入れていくことで情報へのアクセスが良くなります。
また、「自分だけのテキスト」という感じがして、すごく満足度が高い方法でもあると思います。
自分の努力した跡が分かりやすいんですよね。
大事なところにマーカーを引くというのもそうですし、ここはこうだけど後から出てくるこれとの相違点に注意とかの書き込みもあると思います。
デメリット
デメリットとして、まずテキストが汚くなりやすい。
なりやすい、というのは、中にはものすごく字がきれいで書き込んでも汚くならない人もいるのかなと思ったので…
ただ、多くの場合テキストへの書き込みに時間を取られたくないですから段々書きなぐる形になっていくはずです。
アンダーラインにマーカーに書き込みに、となっていくとテキストはごちゃついてきます。
一元管理とはいいますが、一元的過ぎて何が大事なのかわからなくなってしまうということです。
また、自分だけのテキストを作り上げていくということはとても満足度の高い勉強方法ではあるのですが、一方で「やった感」が強い方法なんですよね。
簡単にいうと、やった気になってしまう方法ということです。
最後の大問題として、これは大学受験の勉強を一緒に頑張っていた友人の話なのですが、勉強が進むにつれ、書き込まなければいけないという項目が増えていってしまうという友人がいました。
段々、どれも大事に思えてきて、書き込みが増えていくんです。
模試を受けたら、これも大事だったしこれも書き入れたくなる…テキストには書き込めるスペースがなくなっていきます。
そこで友人は新たに参考書を買いなおして、大事なところを整理しなおして再度書き込むということをしていました。
これは非効率的なのではないかなと思ってしまった出来事です。
行政書士試験においても、勉強が進むにつれ、前に気にしていなかったことが実は重要だったということは結構あります。
そのたびに書き込みを増やしていたのでは、かなり非効率です。
こういったことから、私はテキストには「書き込まない」という結論になりました。
どのくらい書き込まないのか
どのくらい書き込まないかというと、アンダーラインも引きません。
マーカーも使いませんでしたし、一文字たりとも書き込まなかったです。
ただし、テキストの別冊六法だけには、鉛筆でのアンダーラインを引きました。
どういうときに引くのかというと、肢別をといていて、条文が思い出せない時って六法を確認するじゃないですか。
そんなときに調べた条文に薄くアンダーラインを引いていました。
これは、大事だから引くアンダーラインではなくて、次にまた同じ条文を調べたときに「前も分からなかった条文をまた調べたんだ」と自分で気づくために引きました。
で、再度調べたら前のアンダーラインの下にまたラインを引きます。
そうして、何度も引く条文は頻出問題の可能性が出てきますし、自分が苦手とする条文なんだと気づきます。
また、鉛筆で薄く引く理由は、「これに関してはもう大丈夫だ」と自分で確信した時に消せるからです。

情報の一元化はどうする?
さて、情報の一元化について。
これは、私の場合はiPadのノートアプリにまとめていました。
ノートを作るのは非効率的だという人もいるのですが、私は肢別3周目からだったかな、3周やっても間違う問題や×肢の理由が説明できないような問題についてはノートにまとめていましたね。
そもそもテキストには、すでに知っていることやいらない情報も載っています。
そのいらない情報にスペースを取られた中に自分の書き込みで情報を一元化しようとしても、さきほどのデメリットで書いたようにごちゃついてきて見づらくなっていきます。
なので、自分の必要な情報だけを一元化するために、私はノートアプリを使っていました。
また、民法でいえば時効問題をまとめた表や、行政法でいえば行審法と行訴法の違いをまとめた対照表を作りました。
ノートの作り方については、ここでは長くなるのでまた別の記事に譲りますが、こうして自分のノートを作っていきました。
これもやった感の出やすい勉強方法ではあるし、ノートを作る時間がもったいないとは思うのですが、ノートはテキストほど分厚くなりませんし持ち運びもしやすいので適度に使うことで移動中の勉強にも使えて便利ですよ。

というわけで本日は、行政書士試験において、テキストへの書き込みは是か非かについての記事でした。
冒頭でも書きましたが、これは私の主観であり、どうするか迷っている人の参考になればと思って書いた記事です。
テキストに書き込むことが勉強法として確立している人や、書き込みのメリットの方が大きいと感じる人に書き込まないことをおすすめする意図は全くありません。
それでは今日はこの辺で。
このブログでは行政書士試験の攻略法や、合格した後の開業準備などについての記事を書いていますので、よかったらブックマーク等していただき、また遊びに来ていただければと思います。