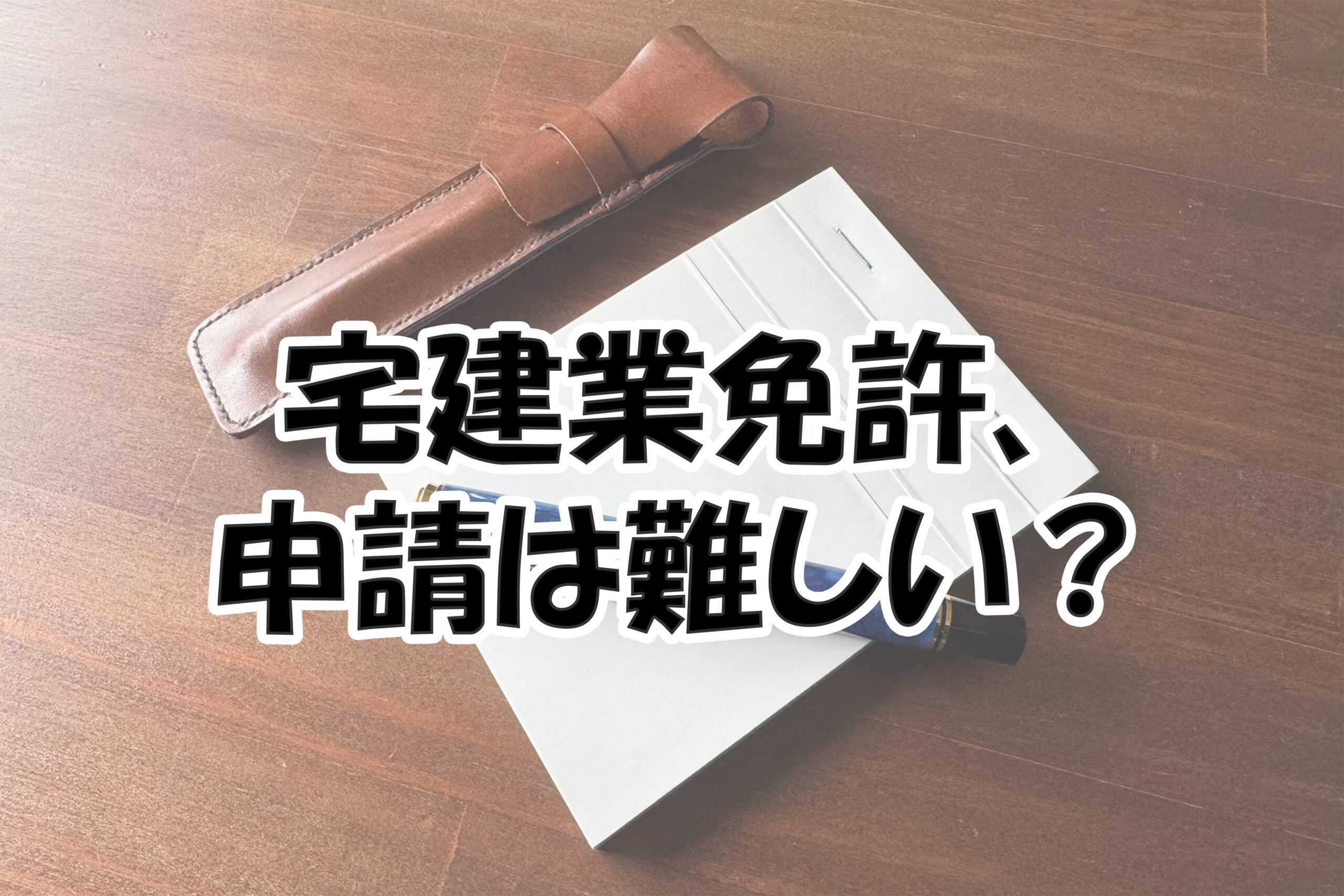こんにちは!行政書士のマツモトです。
本日は許認可申請について。
当ブログは私の趣味日記として書いているので、仕事についての話題はオフィス家具だったり仕事で使えるガジェットの話だったりするのですが、たまには行政書士らしいものをということで…
私は行政書士をしながら、建設業と宅建業の会社を経営しています。
その経験とも合わせて、宅建業の免許を取得するために、自分で申請するのが難しいかどうかを書いていきます。
宅建免許の申請は難しくはないが、面倒くさい
いきなり結論なのですが、申請自体は難しくはありません。
しかしながら面倒くさいのは事実です。
私は行政書士になる前から、自社の宅建免許の更新を自分でしてきました。
入社した時にはすでに免許を取得した後でしたので、自分自身で行ってきたのは更新や変更の申請です。
宅建免許は5年に1度更新しなければならないのですが、更新申請は当然ながら新規申請よりは簡単です。
それでも、かなり面倒くさかったですね。
今となっては行政書士をやっているので、面倒くさいとも言っていられませんが(笑)
なので、慣れていない方や新規申請の場合、おそらく申請自体は可能と思いますが結構な時間はかかると思います。
面倒だと思う人は行政書士に依頼するのが一番簡単かとは思いますが、それだと本記事の意味がありませんので、少しでも参考になるように、どういった申請なのか書いていきます。
まずは申請先の確認
まずは申請先の確認からいきましょう。
宅建の免許には知事免許と大臣免許があります。
多くの場合は知事免許となりますので、本店の所在地の都道府県知事に対し、申請します。
ではどういった場合に大臣免許となるのか?
それは、複数の県に営業所などがある場合です。
例えば、A県に本店、B県に支店があって、どちらでも宅建業を行うとしましょう。
その場合、大臣免許が必要になります。
ここで、宅建業はA県の本店のみで行い、B県の支店は他業種である場合はA県知事免許が必要です。
注意しなければいけないのは、「本店は必ず宅建業の事務所となる」ということです。
どういうことかというと、先ほどの例において、A県の本店では宅建業を行わないんだけどB県の支店で宅建業を行う場合。
この場合、一見するとB県知事免許で良さそうですが、支店で宅建業を行っている場合、本店は宅建業の事務所とみなされますので、大臣免許が必要になります。
こういったことに注意して、どこが申請先なのか把握するところから始めましょう。
多くの場合、支店があっても本店と同一県内ということがほとんどでしょうから、迷う人はあまりいないかもしれませんが、本店が県境にあるような企業様だと2つの県にまたがって支店をお持ちのところも少なくはないようです。
申請書の記載事項は?
申請先の確認が済んだら、次に申請書を用意していきます。
ここでは都道府県に申請するという想定で書いていきますね。
あ、前提として宅地建物取引士が在籍していなければいけませんので、もし誰も持っていないようでしたら、先に資格を取得しておきましょう。
独学でも取得可能ではありますが、あまり学習時間が取れない方は、試験対策講座を受講して効率的に勉強するのがおすすめです。
さて、申請先が都道府県ですので、主たる営業所の所在地の都道府県により対応がことなる場合はありますが、申請書に記載する主な事項としては
- 商号・名称
- 企業である場合は役員等の氏名
- 事務所所在地
- 専任の宅建士の氏名
などなどとなっています。
申請書としては難しい内容ではないので、記載例などに従って記入していきます。
あとは添付書類の準備です。
宅建業の免許には欠格要件(例えば、役員がこういう人だったらダメですよというようなもの)がありますので、それに該当していない旨を誓約する書類であったり、事務所の写真だったり、種類は様々です。
これらを集めるのに、結構時間がかかります。
不備なく整ったと思っても、足りないことが多々あります。
疑問に思ったことは、役所の担当課に問い合わせれば、大抵の場合答えてくれると思います。
申請必要書類の具体例
ざっくりとした概要はおわかりいただけたでしょうか?
ここからは、とある県を例に、具体的な必要書類について書いていきます。
絶対にこの例の通りとは限りませんので、申請先のホームページなどで必要書類を確認してください。
免許申請書
第一面から第五面となっていて、会社の名称や住所、取締役、専任の取引士について記載していきます。
証紙を貼り付ける面もありますが、この納付方法については申請先によりさまざまですので、納付方法をしっかり確認しましょう。
宅地建物取引業経歴書
新規申請の場合、取引業の経歴はないわけなんですが、これも必要です。
新規の場合、最初の免許の欄に「新規」と記入して提出します。
誓約書
これは欠格事由に該当しない旨を誓約する書類です。
欠格事由についてはご存じのかたもいると思いますが、例えば役員が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者というような条件がいくつもあります。
大抵の場合、該当しないとは思いますが、よく確認しましょう。
専任の取引士設置証明書
これは、どの事務所に何人の専任取引士を設置するのかという書類です。
従事する者の数5人に1人は専任の宅建士が必要ですので、下回らないようにしましょう。
相談役及び顧問並びに株主又は出資をしている者※法人
こちらは相談役や顧問について書く書類です。
また、株主についても記入します。
5%以上の株を持っている人について書きます。
事務所を使用する権限に関する書面
事務所リストのような書類です。
新規申請の場合、事務所が自社所有であれば土地建物の登記簿謄本、他者所有であれば、賃貸契約書や使用貸借契約書の写しを添付します。
略歴書
これはよくある履歴書の左半分のようなものですね。
代表取締役、取締役、監査役、専任の宅地建物取引士などの略歴を記載します。
宅地建物取引業に従事する者の名簿
これは社員リストみたいなものです。
個人、法人とも提出が必要です。
注意点として、不動産業の営業さんといったパッと思い浮かぶ人だけでなく主に不動産部門で事務に従事する者も含まれます。
また、代表者、専任の宅建士、政令使用人も記載しましょう。
事務所の写真
事務所の写真は多くなっても大丈夫です。
基本的には、従業者名簿で提出した人数のデスクセットが写っている写真、応接セットなどの写真を添付します。
更新の時は業者票や報酬額表のアップ写真を添付します。
また、更新の時に私自身が事務所の写真として気を付けていることとしては、デスクの写真を撮る際、事務所内部の全景的な写真になると思うのですが、その際に業者票や報酬額表が写り込む画角で撮るようにしています。
私は宅建業のほかに建設業も経営しておりますので、写真のニュアンスとして「きちんと宅建業は宅建業としてだけの部屋を用意しています」と伝わるようにしているということです。
これに関連して、宅建業以外の事業を行っている企業様で新規申請の場合、事務所の写真には他業種の関連のものが写り込まないようにしましょう。
もちろん、宅建業の事務所に独立性が必要なので、ほかの事業ときちんと分けられていれば心配はないかと思いますが…
実際に、知り合いの業者様に「事務所の写真これでいいかな?」とご相談を受けたことがあるのですが
思いっきり「○○工事」と書かれたファイルの背表紙が写り込んでいて苦笑いした記憶があります(笑)
他、公共機関から集める書類
あとは謄本であったり、登記されていないことの証明書であったりといったものを集めます。
これは書いてある通りに集めればよいので、手間はかかりますが難しくはないでしょう。
どんな人が申請するのか
私の経験上、宅建免許を新規申請する人というのは、すでに何かしらの事業を行っている人ですね。
独立開業という話は私自身はあまり聞きません。
というのも、結構お金がかかるんですよね。
会社設立に結構なお金がかかって、事務所を借りて、申請して設備を整えてとなってくると…
これが、すでに事務所を持っていて、宅建業のための部屋を用意できる会社であれば、必要なのは申請費用と保証協会の加入費くらいになってきます(といっても、これでも結構な金額がかかります)
ハードルが全然違うので、結果的に新規申請は何かしらの事業をやっている会社さんが多いということになります。
どちらにせよ、最初の金額だけでなく維持費もかかってきますので、申請する前にしっかり試算して無理なく運営できるかは確認しておく必要があります。
個人で開業を目指すならば、まずは不動産業者さんに就職して、資金をためつつ実務を学ぶというルートがよろしいかと思います。
就職する不動産業者の選定としては、どういった物件をよく扱っている業者なのかもしっかりチェックしておきましょう。
例えば、賃貸物件を主に取り扱っている業者さんだったり売買の仲介を主に行っている業者さんだったり、一口に不動産屋といっても様々です。
余談ですが、新規申請は他業種をすでにやっている会社さんが多いという話と関連して、不動産業だと思って就職したら他業種に回されるという可能性もあります。
就職する際には、どういった業者なのかリサーチするのは本当に大切です。
宅建士の試験に合格し、不動産業に転職したいという人は、専門の転職サービスを利用するのもおすすめですね。
こういった転職サイトもあるので、登録してみるのもよいと思います。
まとめ:ぜひ自分でやってみよう!
この記事は申請の全体像をつかんでいただくためということを主題にしたため、かなりざっくりした内容でしたが、いかがでしたでしょうか?
こんなに面倒なんだから、申請は行政書士に任せて、自分は自分にしかできないことをしよう!
と、言いたいところなんですが、私個人としては自分で申請してみるのもいいんじゃないのかなと思っています。
行政書士としては、こんなことを言うべきではないのでしょうが(笑)
コスパとしてどうなのか、ということを申し上げれば、確かに行政書士に依頼するのは「アリ」です。
行政書士事務所により報酬は前後しますが、大体は10万円前後です。
例えば、あなたの日当たりのお給料が15,000円だとして、7日程度で10万円を超えます。
全く申請をしたことない人が7日で申請まで完了できるかというと、かなり厳しいでしょう。
ただ、宅建業は何かとお役所とのやり取りも発生する業種です。
自分自身で申請することでお役所での対応を練習しておくというのもいいんじゃないのかなと思うのです。
そのうえで、やっぱり自分では無理かなとなってから行政書士に頼るのもいいんじゃないでしょうか。
あ、あくまでこれは経営者の方が自分で申請書を作る前提で書いています。
たまにいらっしゃるのですが、事務員さんに命令して申請書を作らせようという人がいらっしゃいます。
申請に慣れているスーパー事務員さんである場合は別として、普段そういうことをしていない事務員さんに作らせるなんて可哀想なので、そういう場合は行政書士さんに依頼してください。
さて、まとめが長くなりすぎました。
需要があれば、申請書の各項目を深堀した記事も書こうと思います。
それでは今日はこの辺で。