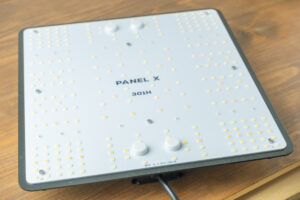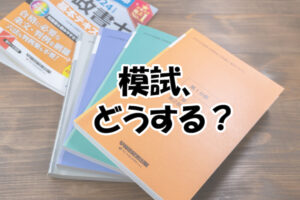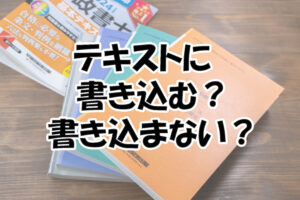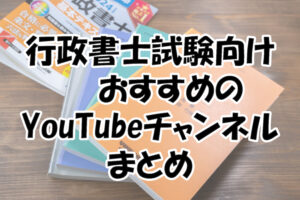こんにちは。行政書士のマツモトです。
本日は行政書士試験の試験勉強期間の睡眠時間についてのお話。
「時間がないから睡眠時間を削って勉強してるけど、大丈夫かな?」
「みんな睡眠時間ってどのくらい取ってるのかな」
こんな疑問をお持ちではないでしょうか。
私も受験生時代にはこの問題には悩んでいました。
勉強が進むにつれて、睡眠に対する位置づけができたので、本日はひとつの参考になればと思って記事を書いています。
筆者は昨年(2024年)の行政書士試験において、独学初挑戦で合格した者になります。
※今回の記事は私のやり方を押し付けるものではありません。あくまで一人の合格者が、受験生時代にこうやっていたという話として受け取っていただければと思います。
※睡眠時間については、日中車の運転をするとか危険な作業がある方は、本記事に記載の事項に限らず、しっかりと睡眠をとって安全を最優先してください。
睡眠時間を削るのは最低限に
いきなり結論なのですが、やはり睡眠時間は大事。
寝不足だと頭が回りませんし、日中の集中力低下にもつながってしまいます。
まぁそんなことはわかってるんだよってことだと思うんです。
ただ、はっきりさせておきたいのは、睡眠時間を削るのは最終手段というか最低限にしたいということです。
で、削るならどこかということですが、私は「朝」だと思います。
つまり夜は早く寝て、朝早起きするということですね。
具体的な睡眠時間
私も社会人受験生だったので、かなり時間がなかったです。
そんななかで、「何時間睡眠ならいけるか」というのを受験勉強初期に試していました。
実際は大学受験の際やほかの国家資格を受験した時の睡眠時間を参考にしたのですが、やはり年齢を重ねるにつれて睡眠に必要な時間が変わっているかなと思ったので実験が必要でした。
結果、私の場合は6時間寝ればなんとかなる。
ということでした。
この時間については人それぞれあると思います。
6時間きると、勉強中に眠くなったりして逆に効率が悪いなと感じました。
で、夜遅くまで勉強して朝ギリギリまで寝るか、夜早く寝て朝早く勉強するか
という選択に迫られます。
私が感じたのは圧倒的に朝の方が勉強しやすいということ。
具体的には夜10時に寝て、朝4時に起きていました。
なぜ夜より朝なのか
これについては、朝の方が頭の回転が~みたいな話ではありません。
もっと、社会人的に…という生活的しばりみたいな話です。
終わる時間が決まっている
睡眠時間を確保するというのが命題なわけです。
例えば夜に勉強していたとしましょう。
この時間までにベッドに入ろうと決めています。
でも、勉強のきりが悪いところです。
どうしますか?
多少就寝時間を過ぎても、ついついきりのいいところまでやっちゃいませんか?
これだとなかなか、何時に寝て何時に起きるというのをルーティン化できません。
一方、朝はどうでしょう?
起きる時間はアラームなどである程度管理できますよね。
話が脱線しますが、私が朝起きるのに使っているのはapplewatchです。

で、決まった時間に起きた後、勉強時間の終わりはどうでしょうか?
多くの人が朝の支度にかかる時間はだいたい決まっており、家を出なきゃいけない時間もほぼ決まってますよね。
私の場合は6時15分に起きなければ会社に遅刻してしまいます。
そうなると、その時間を過ぎてまで、勉強のきりが悪いからと言って勉強し続けられるでしょうか?
無理ですよね。
なので、強制的に勉強時間を終えられるということです。
早朝は子供が寝ている
これは小さなお子さんがいる方に関しての話ですが、当たり前だけど早朝は子供がまだ寝ているんですよね。
この事実はなかなか大きくて、子供が起きている時って、パートナーが子供を見ててくれるとか協力してくれる場合でも気になって勉強に集中できないものです。
では子供が寝静まってから勉強するかというと、子供は何時に寝てくれるかわかりません。
なので、寝ているのが分かっている早朝に勉強時間を設定してしまおうということです。
寝た後なので、体力的に有利
仕事終わりで疲れ切った後に勉強するよりも、睡眠を取って体力が回復した後の方が体力的に有利という理由もあります。
また、体力面でいうと、確かに勉強した後の仕事というのもしんどいですが、仕事は「やらなきゃいけない」という心理が働きますよね。
対して勉強はどうでしょうか?
極論、「やらなくてもいい」もんです。
行政書士試験においては行政書士事務所の跡取りで必ず合格しなければならないとかなら「やらなきゃいけない」になるのかもしれませんが…
なにがいいたいのかっていうと、仕事や家事をした後の勉強ってよっぽどの体力か意志力がないとできないってことです。
【注意】このように書くと誤解されるかもしれませんが、筆者は仕事を「やらなきゃいけない」ものだと自分を追い込むのには反対です。正直、仕事なんて心を壊してまでやる必要はないです。あくまでここでは、勉強と仕事なら仕事の方が取り掛かりのハードルが低いというだけのことです。
というわけで、体力のある朝のうちに勉強をやってしまった方がよいと考えています。
とはいっても眠れないならどうするか
さて、私のケースでいうと22時から4時までの6時間睡眠ということになるわけですが、22時きっかりに眠れるわけじゃないですよね。
私の場合、どうしていたのか書いていきますね。
まず、21時までに入浴を済ませます。
お風呂あがってすぐはお布団に入りたくないですからね。
お風呂上りは明日の準備や家事などをします。
21時45分ごろ布団に入ります。
問題は15分で入眠できるかどうかということになります。
私の場合、これがなかなか難しかったので工夫しました。
まず、Youtubeで自然音を聴くようにしました。
これについてはASMRを聴くのに最適なイヤホンを見つけたので、これを使うのがおすすめです。

この音を聴くと寝る時間だと自分自身に教えるようにしました。
重要なことは、「眠れなくても焦らないこと」です。
寝なきゃ!と思うほどに眠れなくなるものです。
なので、寝れなくても仕方ないくらいの気持ちでいるのが大切です。
また、寝る前の自然音を聴くこともそうなのですが、入眠前をルーティン化することで、眠りに入りやすくなります。
このとき、スマホを見ながら寝たりゲームをしながら寝転んだりしないことです。
眠れなくても横になって体に休息を与えてください。
先ほどもApplewatchで起きていると書きましたが、睡眠についてもApplewatchに入れているアプリを使って計測していました。
この計測アプリによると、自然音を聴きながら眠ることに決め、入浴時間も決め、布団に入る時間も決めてから、ほぼ毎日15分以内に眠りにつけるようになったのが記録でも明らかになりました。
どうすれば入眠しやすいかは人それぞれだとは思いますが、一つの参考になればうれしいです。
この勉強時間で足りる?
さて、上記の時間に眠るということは、家に帰ってきて夜勉強する時間ってほとんどないですよね。
この勉強時間で果たして足りるのでしょうか?
勉強の仕方にもよりますが、私は足りると思います。
一般的に行政書士試験に必要な勉強時間は500時間~とされています。
私の場合で計算してみましょうか。
朝4時に起きて6時まで勉強していたので、これだけで2時間の勉強時間があります。
会社への移動時間等々でなんだかんだ1時間は勉強できます。
そうすると1日に3時間勉強できるわけです。
500時間に到達するのに1日3時間勉強だと約166日ですよね。
つまり半年かからないくらいで500時間を達成します。
もちろん、現実はこのように決めた通りにはできませんし、500時間勉強したからって中身がなければ合格しません。
ただ、勉強時間が足りるのかどうかという点については「足りる」という結論になると思います。
睡眠をしっかりとって、効率よく勉強しよう!
社会人はとにかく時間がないです。
ならば作り出しましょう。
時間を作りやすいのは朝の時間帯です。
体調的な理由で朝がどうしてもだめだということでない限り、私は朝の時間帯をおすすめします。
そのうえで、睡眠時間の確保も大事であるため、布団に入ったらできるだけ早く眠りにつけるように工夫をしましょう。
勉強時間が確保できるようになったら、せっかく勉強するからには効率よく勉強していきましょうね。
効率よく勉強するためのアイディアは当ブログにもたくさん記事がありますので、よかったら勉強の休憩の時にでも読んでみてください。
最後に、仕事や勉強は健康あってのことです。
なので自分の健康や家族の健康を優先してください。
無理しないでくださいね。
それでは今日はこの辺で。