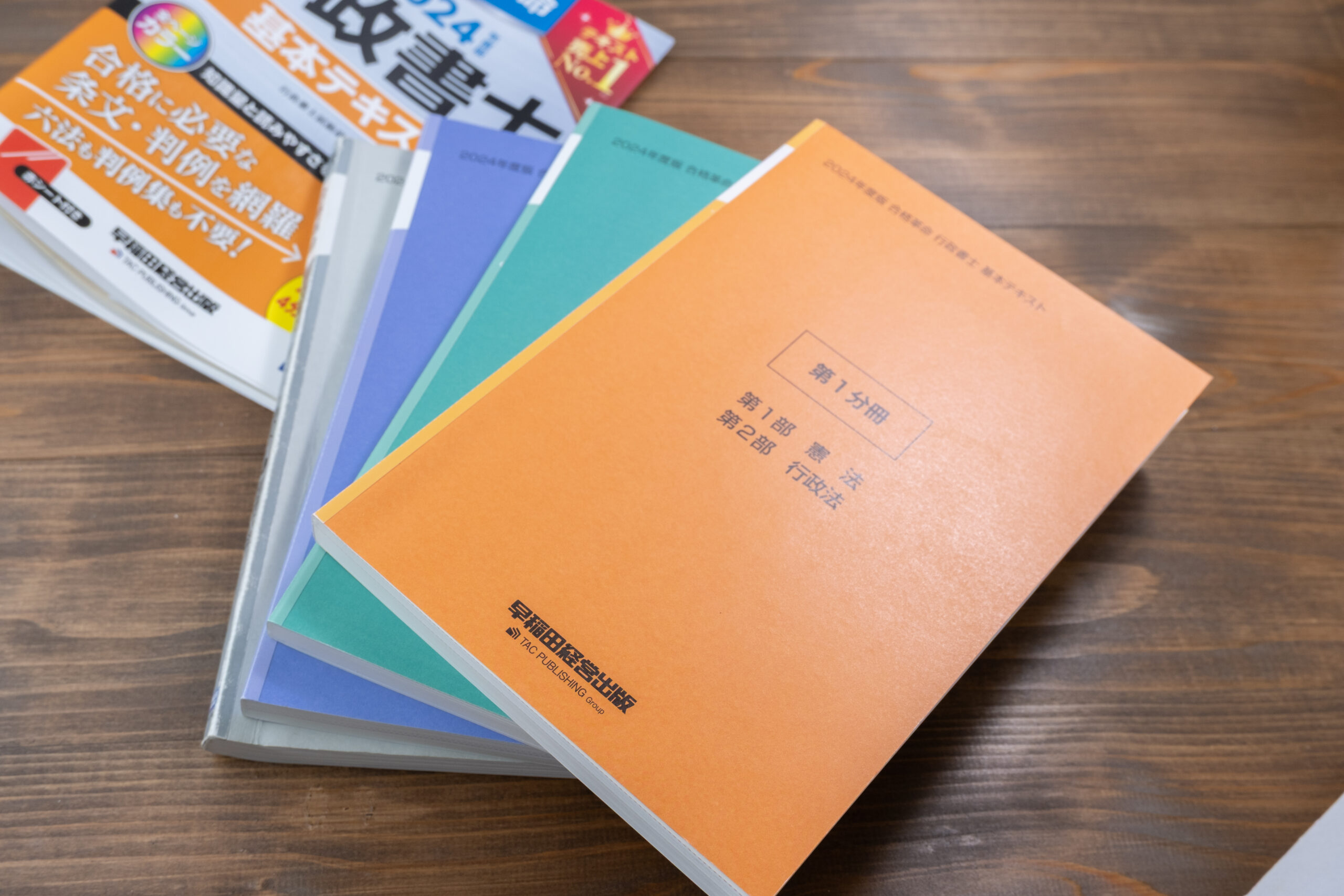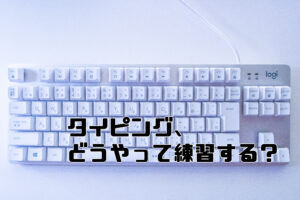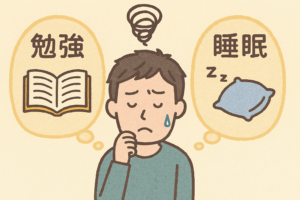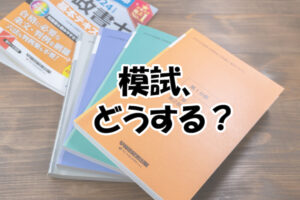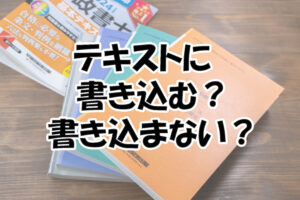こんにちは。行政書士(登録申請中)のマツモトです。
本日は私の合格体験から、実際の勉強スケジュールについて書いていきます。
よく私のX(Twitter)アカウントの方に、「今の時期にこれをやってるのは、すでに遅いですか?」のようなご質問をいただきます。
独学の場合、自分のペースで進められるのがいいところなのですが、やはり他の受験生や合格を勝ち取った元受験生が同じ時期にどのくらいの進行度だったのかが気になる人は多いようです。
それでは早速本文に入っていきましょう。
今回は内容的に文章ばかりで画像もなく、退屈な記事になってしまうかもしれないので、読むのに飽きてしまったら私の他の記事でも読んで息抜きしてくださいね。
行政書士試験を志す人なら、私の事務所開業準備記事なんかは面白くよんでいただけるのではないかと思います。
また、本文各所で出てくる教材についてですが、教材の説明を一緒にしてしまうと長くなるので、別記事でまとめています。
そちらもご参照ください。
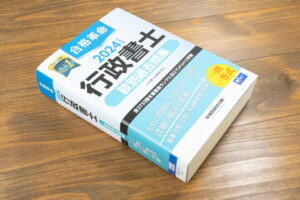
勉強開始:1月~2月
まず、私が勉強を開始したのは行政書士試験を受けた年の1月です。
1月2月では民法を集中的にやりました。
スーパー過去問ゼミ(スー過去)というテキストがあるのですが、こちらが特にわかりやすかったのでおすすめです。
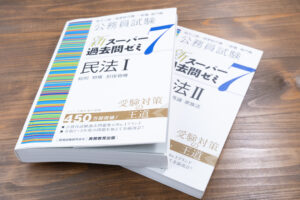
上の記事にスー過去についは詳しく書いています。
なんで民法からなのかという点ですが、法律系の資格は最初とっつきにくいんですよね。
行政法なんか特にそうなのですが、普段役所とそんなに関わることなんてないじゃないですか?
最近では住民票とかもマイナンバーカードを使えばコンビニで取得できる時代だし(自治体による)
その点、民法であれば日常生活に置き換えて考えられます。
例えば、民法のややこしい分野に使用貸借と消費貸借なんてものが出てきますが、私の場合、ご近所さんとの醤油の貸し借りで置き換えて考えてみたり、建設業を経営しているので、知り合いの業者との重機の貸し借りに置き換えて想像してみたりしました。
また、行政書士試験には商法会社法という法律も出てくるのですが、商法は民法とつながりが深い(勉強していくと特別法なんて言葉がでてきます)ですので、民法の基礎をまずはしっかり固めておく必要があると思います。
ということで、民法だけは行政書士試験向けのテキストのほかに、スー過去に取り組みました。
これを2カ月かけて2周しました。
スー過去には民法Ⅰと民法Ⅱがあるのですが、どちらも2周ですね。
3月~本番
くくり雑すぎない?と思われたかもしれませんが、ここからは同時進行のものが多いので…
3月に入ると、私は合格革命の肢別問題集に取り組み始めました。
スー過去になれていたので、肢別の区分に合わせて、対応する合格革命テキストを読み、実際に肢別をやるという感じで1周目をやりました。
2周目からはテキストは見ていません。
肢別をやっていて分からなかった時のみ、該当箇所を見るようにしました。
また、ノートにまとめたり何か書いたりするのは、2周目が終わるまでは全くやっていません。
3周目で間違った理解をしていたり、何回も間違ったりしたものを簡単にiPadのノートアプリにメモをとりました。
ざっくりまとめると
項目ごとに対応ページが書いてあるので、肢別とテキストはシリーズを揃えた方がよいです
多少わからなくても、しつこくテキストを読んだり調べたりするとこの段階では非効率かと思います。
ここから、間違った問題や間違った理解はノートに書いたりネットで調べたりしました。
また、判例問題の気になるものは判例集を見たり最高裁のHPに判例を読みに行ったり。
苦手な分野が見えてきます。集中的にYoutubeなどの解説動画を見るなどして苦手を潰していきます。
肢別はこんな感じで回していきました。
特に、3周目からは肢別からノート、肢別からテキスト、肢別から判例、肢別から六法…といった感じで、肢別を中心に添えた学習をしました。
参考までに、本番まで肢別を何周したかですが、私の場合は科目によっては8周、全体でいうと7周しました。
6月~本番
記述式問題集には、6月中旬から取り組みました。
集中してやるというより、肢別に飽きた時と勉強を始めるときに時間を決めて取り組みました。
だいたいのペースでいうと、平均して1日5問から10問くらいでしたね。
これは何でやったかというと、肢別の周回によるマンネリ化対策と、肢別でわかった気になっているけど実際はわかってないという分野の洗い出しです。
どういうことかというと、気を付けていても肢別の正誤だけ記憶してしまって何となく解けてしまっているものがあるんですよね。
そこで、記述式の問題をやってみると、書けない。
書けないのは、単に記述に慣れてないというのもありますが、大きな理由は、やはり知識がしっかり身についていないからです。
そういった「わかった気になっている」箇所を割り出すためにやりました。
5月ごろ~
すみません、ここまで書いたものはカレンダーに記録していたので、いつからやったのかはっきりわかるのですが、ここから先は、そういえばこれもやったなというものなので、はっきりといつから取り組んだのかはあやふやです。
5月ごろだったと思いますが、一般常識の足切りがこわくなりました。
そこで、ニュース検定のテキストを読んだり、Youtubeで時事問題で出そうなものの解説動画を見たりしました。
ニュース検定のテキストが役に立ったかどうかなのですが、これをがっつりやっても効率は良くないと思います。
ただ、ほかに対策方法が限られていますので、読書代わりに毎日少しずつ読んでもいいかなと思います。
私はどちらかというと、Youtubeの解説動画が役に立ちました。
景気であったり、政治であったり、いろいろな分野をみました。
動画を観るだけなので、勉強と違ってストレスも少ないですし、食事中に(お行儀は良くないですが…)よく観ていました。
時期によっては模試
最後に、模試についても書いておきますね。
模試については、私はLECの模試パックを購入して取り組みました。
LECの模試については、内容はとてもよかったのですが、私の取り組み方がよくなかったなと思う点があります。
これについては大事なところなので、また後程記事にします。
書き終わったらこちらの記事にもリンクを張りますので、ぜひ読んでみてください。
スケジュール管理は大事!
さてまとめていきます。
肢別は周回が増えるごとに、早く回れると思っていませんか?
実はそんなことはありません。
少なくとも、私は時間がかかるようになっていきました。
なぜかというと、肢別周回の最初の方は、「何がわからないかわからない」状態だからです。
分かった気になって飛ばしていたところも、周を重ねるごとにわからないところが見えるようになってきます。
そのため、六法で確認したり判例を確認したりする機会が増えて、結果、時間がかかるようになっていくのです。
それ自体は勉強になっているので良いことなのですが、あまりだらだらやると効率がよくありません。
私の場合は、iPadのノートアプリでカレンダーを作成して、例えば「今日は行政法の3周目で何ページから何ページまでやった」という記録を付けるようにしていました。
こうすることで、前の周に比べて異常に時間がかかっているなどといったことがすぐわかるようになります。
先のスケジュールを立てるのはもちろん大事なのですが、過去のスケジュールを確認するのも大事だと私は思っています。
とりとめのない文章になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。
細かいところまでは書けていませんので、わからないことがあったらコメント欄で質問してくださいね。