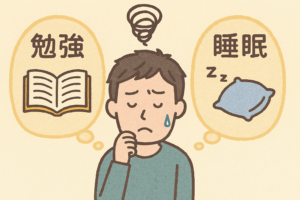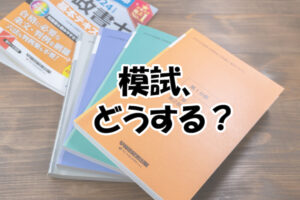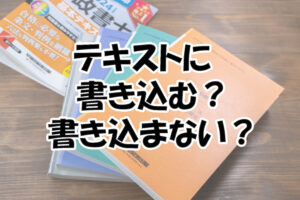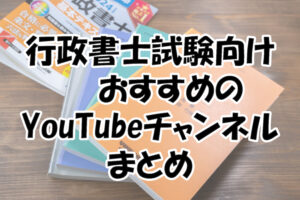こんにちは、行政書士のマツモトです。
本日は行政書士試験について。
私は昨年(2024年)の試験に初挑戦独学で合格したものです。
私のSNSの勉強アカウントでよくされる質問なのですが、肢別とウォーク問のどっちをやればいいのかという問題。
本日はこれをテーマに書いていきたいと思います。
結論:どっちでもいい
結論から書きます。
どっちでもいいです。
どちらにもメリットがありますので、より自分にとってメリットが大きい方を選べばよいです。
じゃあそれぞれのメリットってなんだよってことになると思いますので、主観ではありますが肢別本とウォーク問のそれぞれのメリットを書いていきたいと思います。
繰り返しになりますが、以下に書いていくメリットはあくまで私の主観です。
一番いいのは、自分で比べてみて選ぶ方がよいと思うのですが、時間もないと思いますのでひとつの参考にしていただければと思います。
行政書士試験の問題形式
肢別とウォーク問を比べる前に、ご存じかとは思いますが行政書士試験の問題形式について書いていきます。
行政書士試験には5肢択1式の問題と多肢選択式の問題、記述問題があります。
最も配点が高い五肢択一式問題で、これをいかに攻略するかが試験の明暗を分けることになります。
肢別本とは
有名どころは合格革命の肢別本ですね。
私が購入したのも合格革命の肢別過去問集です。
上のリンクから購入できますが、電子書籍版と書籍版がありますので間違えて購入しないよう注意してください。
肢別の特徴としては、名前の通りで過去問の肢の正誤を一問一答形式で問うという形式になっているところです。
例えば、過去の試験問題の問10「以下から適当なものを選べ」という問題があったとして、選択肢は5つなわけです。
この5つを分解して、さらにより重要な肢が正しいか間違いかを問うという形になっています。
いわゆる〇×問題を解いていくということですね。
左側のページに問題、右側のページに答えと解説となっており、右側のページを隠しながら問題を解いていくという感じです。
肢別のメリットとして、重要度の高い肢を選んで掲載されているため、効率的に勉強ができますし、×の選択肢の何が間違いなのかを説明できるくらいになれば、応用もききます。
ウォーク問とは
ウォーク問は、肢別と違い過去の重要問題がそのままの形で掲載されているものです。
例えば、〇年度の何問みたいな感じですね。
本試験と同じ五肢択一形式なので、間違った選択肢を切る作業になれることができるのがメリットです。
科目ごとに勉強できるのは肢別と同じなのですが、ひとつひとつの正誤を判断していく肢別と違い、5つの選択肢から正解を導くという本試験に近い形式で勉強を進めることができます。
ただ、後述しますが私はウォーク問を選びませんでしたので、これ以上のメリットについては正直わかりません。
「どっちもやる」はダメなの?
そもそもどっちか選ばなきゃいけないのか?と疑問に感じる人も多いと思います。
また、実際の受験生でもどちらもやっている人も少なからずいますね。
ただ、私はどちらか選んだ方が良いと断言します。
どちらかしか勉強しないとなると、カバー範囲が狭まって不安に感じる人もいるでしょう。
でもよく考えてください。
例えば、肢別を中途半端にしたままウォーク問に手を出した人と、肢別を完璧に仕上げた人の、どちらが合格確率が高いと思いますか?
何がいいたいかというと、受験生のほとんどが社会人である以上、時間が限られているわけなのでどちらかに集中した方が良いということです。
肢別かウォーク問かを主軸に据え、+αの知識として肢別やウォーク問で出てきた判例を判例集を使って調べるとか試験用の六法をひくとかした方が良いです。
肢別とウォーク問はどちらも過去問ですので、過去問をわざわざ形式違いで2つもやる必要は私には感じられません。
なので、肢別+判例集+六法だったりウォーク問+判例集+六法だったりというように学習を進めていく方がよいと思います。
私が肢別を選んだ理由
私も受験生時代に肢別にするかウォーク問にするか悩みました。
書店で二つを見比べながら思ったのですが、ウォーク問のメリットとして本試験の形式になれることができるというのはわかりました。
でも、それって模試で十分じゃない?と思ったんですよ。
いくらウォーク問をやっても、どのみち模試は活用した方が良いです。
となれば、模試を解くなかで五肢から正答肢を選ぶ練習が十分できるんじゃないかなと思ったんですよね。
また、肢のひとつひとつをよく考える、ひっかけ問題に引っかからないようにするということにおいて、肢別の方がよりメリットが大きいと感じました。
そういったわけで、私は肢別を選びました。
逆に、資格試験に慣れていない人や本試験でのタイムオーバーが怖い人はウォーク問を使って学習することで、誤肢を切る感覚を身に着けられると思います。
なので、これは本当にどちらのメリットをより大きく感じるかで選んでよいと思います。
あと、注意点なのですが、すでに学習を進めている人でどちらかを選んでいる人はこの記事に左右されず、今使っているものを使い続けた方がよいでしょう。
すでに5月ですので、今更切り替えるより今使っているものを仕上げていった方が良いと思います。
肢別を使った学習をする上での注意点
最後に、私的肢別勉強法を少し書いておきます。
肢別を使った学習にはコツがあります。
それは、〇×だけを見た学習はしないということです。
肢別を何周も回していると、この問題は×だ、というふうに覚えてしまいます。
ただ、そこで×という判断だけで終わってはダメです。
なんで×なのかまで含めてこたえられるようにしないと、勉強した意味がありませんし応用もききません。
また、〇肢についても判例問題だったらなんの判例か思い浮かぶかであったり、問題文のここがこう変えられて×肢として出そうだなだったり考えながら解く癖をつけると記憶に定着しやすいと思います。
詳しい肢別勉強法については本記事との趣旨がずれますので、また別記事にて書きますね。
それでは今日はこの辺で!