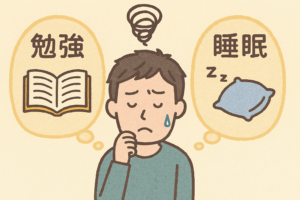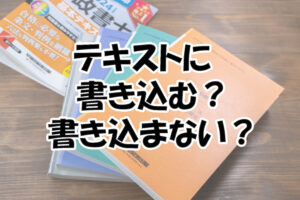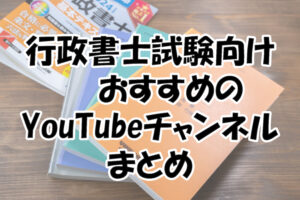こんにちは。行政書士のマツモトです。
本日は行政書士試験について。
最近、「もう試験まで半年ですが、今からでも間に合いますか?」という質問をいただくことがあります。
なので本日は、半年前からでも行政書士試験の勉強は本番までに間に合うか。
というテーマで書いていきます。
ちなみに筆者についてですが、昨年(2024年)の行政書士試験において初挑戦独学で合格した者です。
結論:間に合う
大丈夫です。間に合います。
ただ、正直、やり方次第です。
一般的に、行政書士試験に合格するための勉強時間は500~1,000時間程度といわれています。
半年ということなら、約180日間あるので1日平均3時間勉強できれば単純計算で540時間勉強できることになります。
数字の上では合格に必要な勉強時間の圏内には入ります。
とはいっても必要最低限の時間数といえるので、最大効率で勉強をする必要がありますよね。
ということで、1日平均3時間勉強するという前提で、私なりの効率的な勉強方法について書いていきます。
私も500時間程度で合格したので、ある程度効率的な勉強方法で勉強できたと思っています。
参考にしていただければ嬉しいです。
なお、以下の勉強法で勉強すれば必ず合格できるという保証はありません。あらかじめご了承のうえ、参考にするかどうかはご自身でご判断ください。
主軸を肢別本に据える
私のおすすめは過去問にベースをおきつつ、+αで知識を付けていくという方法です。
過去問としては、私が使ったのは肢別本ですね。
ウォーク問の方が解きやすいなら、そちらでも構わないと思います。
肢別本がいいかウォーク問がいいかについては過去記事もご参照ください。

効率重視というなら、肢別本がおすすめではあります。
では具体的な勉強方法に移りますね。
といっても、とてもシンプルです。
肢別本をひたすら周回する。
これだけです。
肢別本は憲法、行政法、民法といった具合に科目ごとに問題が出てきます。
形式は一問一答形式で、問題文の正誤を判断していきます。
材料
さて、詳しい勉強方法に行く前に、最低限必要な教材を列挙しておきます。
- 合格革命 肢別過去問集
- 合格革命 基本テキスト
- 記述問題集
- 模試
時間もないので、これだけでいきましょう。
具体的な勉強方法
それでは勉強方法の詳細を書いていきます。
テキスト該当箇所読む→肢別解く
難しい問題にひっかかってもとりあえず進めていく
3周目になっても意味が分からない問題はYouTube等で解説動画を閲覧。
3周目でも間違う問題はテキスト付属の別冊六法やテキストの内容を確認する。
必要があればノートに簡単にポイントをまとめる※きれいなノートは作らない
基本的には3周目と同じ。記述式問題集を1日の勉強開始時の30分間ほどやるか肢別に飽きたときに挟むなどして記述対策をしておく
資格試験に慣れている人であれば、いきなり肢別をといてその後にテキストで確認でもいいと思います。
初学者は、肢別のパートごとにテキストの該当ページが書いてありますので、その部分を読んでから肢別を解いてみるのがおすすめです。
 マツモト
マツモト1周目はわからないことがあっても、ガンガン進んでいくことが大事だよ!
法律系資格のあるあるだと思うのですが、わからない部分があっても、先を勉強していったときに「あの時のあれはこういうことか」みたな感じでわかることが多いです。
なので、わからないところで止まって考えるよりも、ひたすら進んでいくことをおすすめします。
2周目はテキストを読まず、肢別本を進めていきます。
3周目になっても意味がわからん…というような難解な箇所(例えば民法の法定地上権や行政法の形式的当事者訴訟など)は、たいていYouTubeに解説動画を上げてくれている人がいるので、そちらを閲覧してみる。
また、正誤判断を間違った場合に自分で別冊六法やテキストでわかる範囲であれば、間違いやすいひっかけに注意するようノートにまとめるのもありです。
ノートを作るうえで、意識すべきことは「本番前日の自分のために作る」ということです。
きれいなノートであっても、なんでもかんでも書いてあるようなノートは前日に見るのに適しません。
前日確認するためのノートですから、○○と××は勘違いしやすいので注意!くらいのもんでいいです。
4周目からは基本的に3周目と同じ手順でよいです。
ただ、肢別にも飽きてくるころだと思いますので、1日の勉強時間開始時やキリのいいところなどで記述式問題集を解くといいかなと思います。
隙間時間を活用しよう
ここまでの勉強方法は家などで座ってしっかり勉強できるときの勉強方法です。
通勤時間や家事の合間などの隙間時間にも肢別周回だけでは身につかない知識をつけていきましょう。
- 時事問題系の解説動画を観る
- フォーサイトの判例解説動画を観る
- 自分で作ったノートを見る
- 別冊六法の憲法、行政法を読む
私が隙間時間に行っていたのは上のような勉強です。
最初の2つはYouTubeを利用したものですね。
時事問題系はある程度模試などを解いてみて、気になるor全然知らない知識といった時事問題系の解説動画を観ます。
これだけでも一般知識の方の足切りを免れるかもしれません。
私の場合、○○景気がどうのこうのって模試で出てきたときにちんぷんかんぷんだったので、日本の景気について解説してくれている動画を観たりしてました。
また、判例問題が多い行政書士試験ですので、フォーサイトの重要判例を解説してくれている動画をよく観ていました。
観ていたというより、家で家事をしている時にラジオのように流していましたね。
また、肢別を周回するうちに蓄積された自分の作ったノートを見返したり、別冊六法で憲法や行政法の条文を読んだりしていました。
肢別に飽きたら模試を入れよう
肢別も、何周もしていたら飽きてきます。
そんなときに、模試をやってみることをお勧めします。
市販模試でもいいので、1回分やってみることで一般知識ではどんな問題が出るのかといったこともだいたい把握できますし、自分の力が現状どんなもんかもわかります。
大事なことは、しっかり見直しつつ、あまり時間をかけないこと。
たまに1回の模試の見直しに2週間とかかける人がいますが、私の感覚だと1週間以内に見直しは終えた方がよいです。
あくまで主軸は肢別周回です。
模試については過去記事でも書いています。
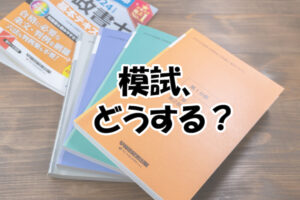
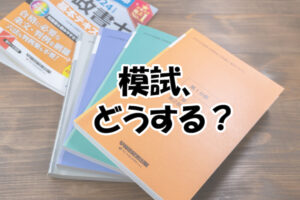
まとめ:ひたすら周回
最低限の勉強時間でなんとか行政書士試験の合格率を最大まであげるというコンセプトの記事でした。
勉強時間が少ないので、やることを絞って、主軸は肢別の周回ということにしました。
実際、私も肢別本周回を主軸に、判例集や別冊六法で知識を蓄えていきました。
すでに勉強方法を確立している人はこの方法に変える必要はないですが、もし今から勉強方法を考えようとしているならこの記事を参考にしていただければと思います。
残り時間はあまり多くないように感じるかもしれませんが、半年あるので、頑張っていきましょう!
予備校を使うのもおすすめ
本記事では独学を前提に書いてきましたが、短い時間で最大効率で勉強するとなれば、予備校を使うのもひとつの手です。
例えば有名どころの伊藤塾では短期間で合格を狙うコースもありますので、みるだけ見てみてはいかがでしょうか。