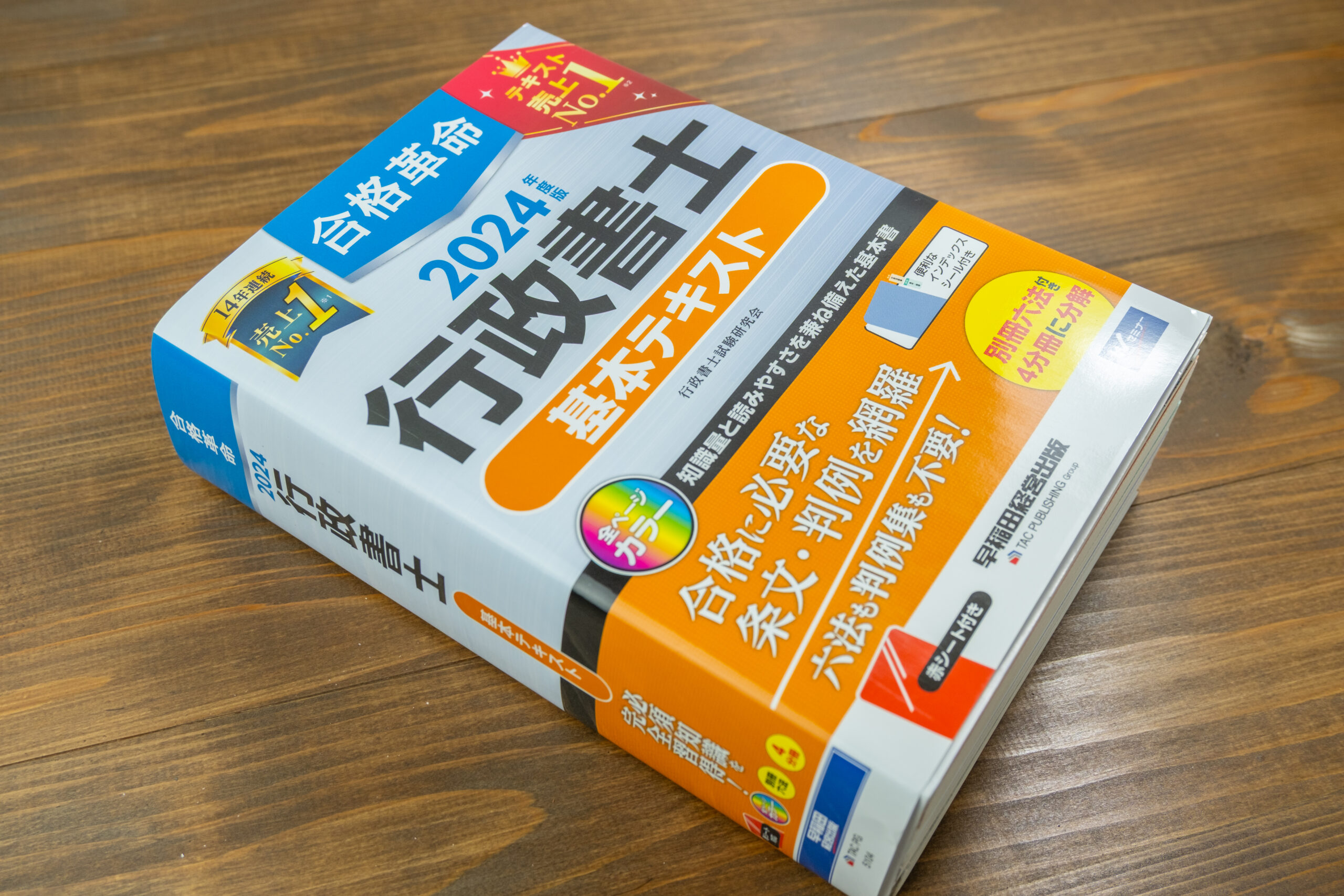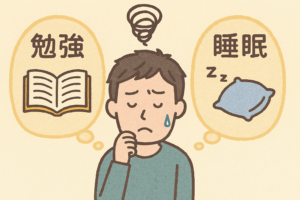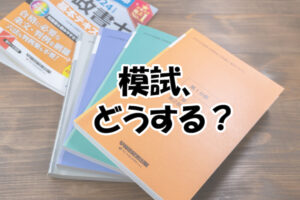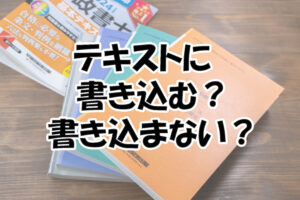こんにちは、行政書士(登録申請中)のマツモトです。
本日は前回に続いて行政書士試験の行政法の勉強の仕方についてです。
前回も私については紹介したので、プロフィールが気になる方は前回の記事をご覧ください。
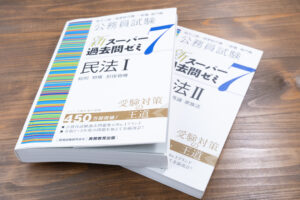
簡単にいうと、独学の初学者で昨年の試験を1発合格したものです。
それでは行政法編、行ってみましょう!
この記事は筆者の合格体験をもとに、参考にしていただくためのものです。
勉強方法は人それぞれのため、すでに確立した勉強法をお持ちの方に、こっちの方がいいよ!とおすすめするものではありません。
行政法ってどんな科目?
さて、行政書士試験というくらいですので、同じ名称である行政法が最も重要な科目ということになりますよね。
行政法といっても、実際には「行政法」という名前の法律はなく、試験的な内容は
- 行政法の一般的な法理論
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 国家賠償法・損失補償
- 地方自治法
といったものになっており、一番最初の法理論には行政組織法や行政作用について、強制措置などが含まれます。
行政書士試験の中で最も配点が高い科目となり、たくさんの問題が出ますが、理解すれば行政法ほど点数を稼げるものはありません。
ただ、地方自治法は「まったくわからない」という問題も出る可能性があるのですが、出題はあまり多くないので基本的なことを押さえておいて取れなければ仕方ないと割り切った方が良いでしょう。
全体的に言うと、地方自治法は間違っても仕方ないが他の行政法の得点は「絶対に」落とせない。
というのが最終期の受験生時代の私の感覚でした。
しかしながら、勉強を始めた最初の方は、行政法というとっつきにくい法律に悪戦苦闘していた記憶があります。
とにかく、イメージしづらいんですよね。
かといって、丸暗記でどうにかなるような甘い試験ではありません。
そこで今回の記事で行政法の効率のよい勉強方法を紹介していこうと思います。
ざっくり行政法の流れをつかむ
まず、勉強方法ですが、他の科目と同じで基本は肢別過去問を回すことです。
私の場合、合格革命の肢別の分類ごとに適応する合格革命のテキストページが書いてありますので、まずはそこを読んで肢別を解いての繰り返しで1周目を回しました。
それから2周目、3周目と肢別を回していくわけですが、その中で大切なことに気づきました。
それは、行政法の科目に属する法律はつながっているんだということです。
別々のものとして勉強していると、なかなか理解できないのが行政法だと思います。
ざっくり説明しますね。
例えば、行政(役所)のやることで私たち国民に最も影響のあることに「処分」があります。
ただ、制限なく役所が処分できてしまうと、国民にとって多大な不利益を生むわけです。
そうならないために、行政法の各法律があると理解します。
つまり
役所が処分を下すにも、種類がありますので、場合によりどんな処分となるかという範囲です
役所が処分を下そうとする前に、役所に対し「言い訳」する機会が与えられます。
逆に言うと、そういった弁明の機会を与えなければ処分できないといった「手続き」が必要ということです
続いて、いざ処分が下った場合、不当な処分だと訴えたい場合もあるでしょう
ただ、裁判所に訴え出ても時間がかかる。
そこで処分をくだした役人の上司に不服を訴えることができる行政不服審査法の出番です。
とはいっても、やはり同じ役所のすること…
行政側に有利な判断をされてしまうかもしれません。
そこで、時間はかかりますが、裁判所に判断してもらうことも可能です。
ここで登場するのが行政事件訴訟法です。
さて、ざっくりではありますが、上記のような感じで行政法に含まれる各法律はつながっているのです。
もちろん、行政法では処分ばかりが出てくるわけではありませんが、各法律のつながりを意識することが理解につながっていきます。
自分が何を勉強しているのか常に考える
法律のつながりが大事だというのは、ここからの話につながります。
例えば、行政不服審査法と行政事件訴訟法には似たようなケースについて規定している部分があります。
なので、自分が今どっちを勉強しているのかということを考えていなければ、こんがらがってくるんですよね。
これが行政法を難しくしてしまう原因です。
それぞれの法律がなぜ存在していて、その意義は何なのか
これを意識し、今どちらを勉強しているのか
例えば、今行政事件訴訟法を勉強していたとして、不服審査法ではどうだったかな?やここは不服審査法と違うところだなと考えながら肢別をまわすのがとても大事ということです。
ただ単に○×が合ってたとか間違ってたとかいうのだけ確認して勉強していたら、なかなか点数はあがりません。
判例について
法律系の資格につきものの判例についてです。
判例というのは、ものすごく簡単に言うと、「こういう事件があって、その時裁判所はこう判断した」という事例のことです。
実際に、法律が裁判でどう解釈され、どういう判決が下ったのかということで、試験でもよく出てきます。
私が最もよく使った教材である肢別過去問にも判例から出ている問題が多くありました。
そこで、この判例をどう勉強するかなんですが
判例に興味を持つ
これにつきると思うんですよね。
例えば、テキストでも「こんな判例があったよ」なんて紹介があります。
そこで、一歩踏み込んで、どういう事件だったのか最高裁判所のホームページで読むことができるので、それを読んでみるのも楽しいです。
また、そうして探したものは記憶に残りやすいうえに、他の判例問題で知らないものがでても「裁判所はこういう判断はくださなそうだな」というような勘が働きやすくなります。
もちろん、全部の判例問題に対し調べる必要はありませんし、その時間もないですが、判例に興味をもって接するのはとても大切だと思います。
だって考えてみてください。
判例ってことは、実際に誰かの身に起こったことなんです。
そしてその誰かは、最高裁判所まで争ったんですよ。
途方もない労力だと思います。
そう考えると、なんでそんなことが起こって、どう裁かれたのか、気になってきませんか。
さて、判例について書いていくと長くなるのでこの続きは、判例を勉強することが重要になる憲法についての記事に譲ろうと思います。
まとめ:行政法はそれぞれのつながりと違いを意識することが大事!
今日の行政法に関する記事はいかがでしたでしょうか?
行政法は条文から問題が出ることも多く、それぞれの違いをはっきり意識できていればとれる問題が多いです。
コツをつかむまではとっつきづらく難しい科目だと思いますが、逆にコツをつかめば得点源にできる科目です。
また、行政法の点数が低いと行政書士試験に合格するのはかなり難しくなってしまいますので、ぜひ頑張ってマスターしましょうね。
そのほか、行政法についてわからないことがあれば、コメント欄で質問いただければと思います。
私は予備校の講師ではないので、適格に答えられるかわかりませんが、私にわかる範囲でお答えしようと思います。
それでは、今日もありがとうございました。