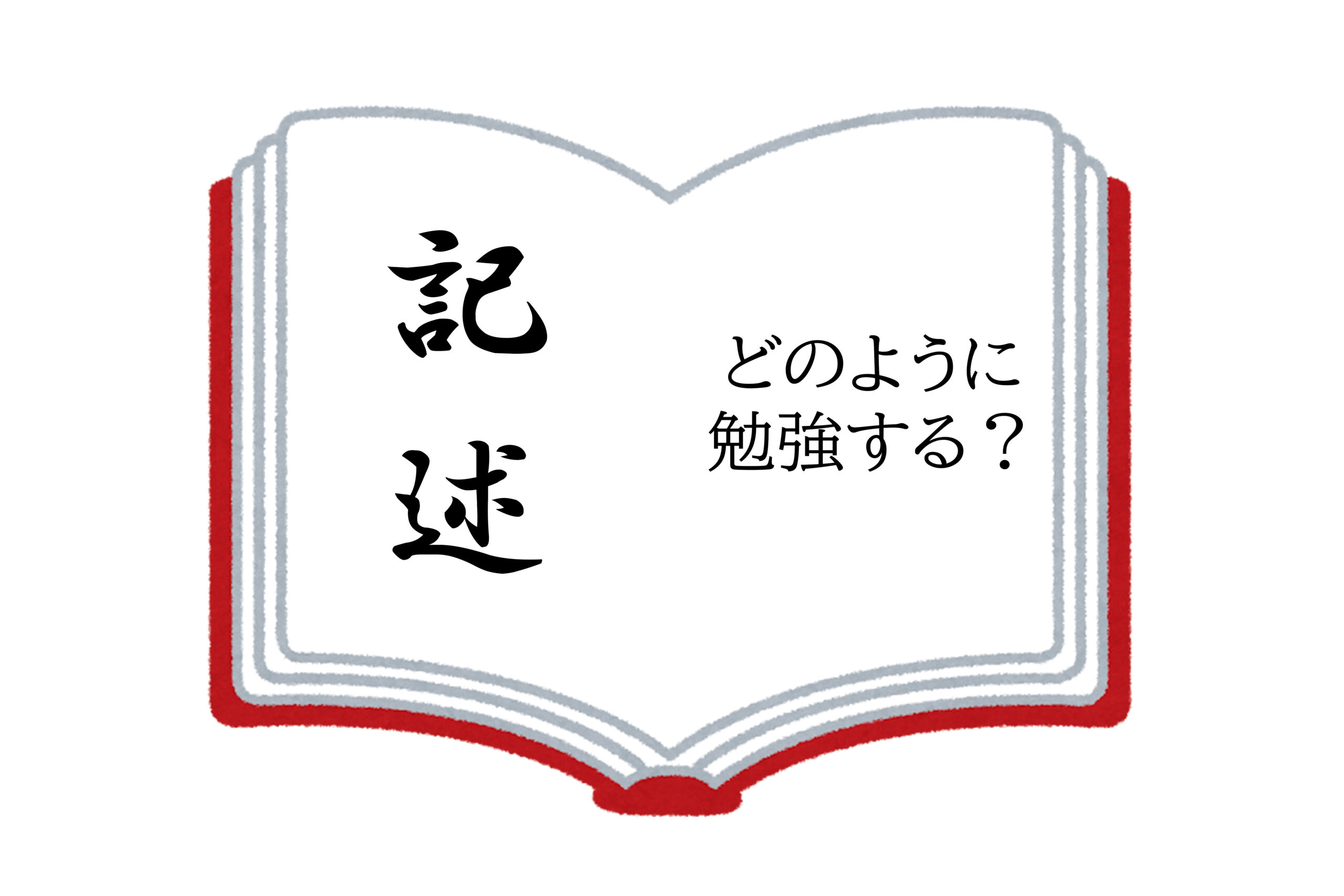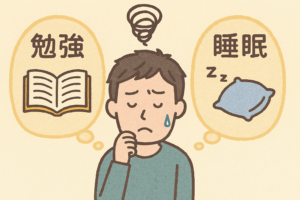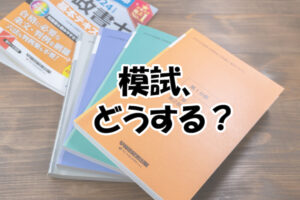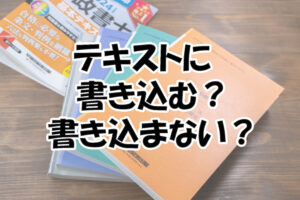こんにちは!行政書士のマツモトです。
本日は行政書士試験の記述について。
よくマークシートだけで合格点の180点を目指しましょう!というのを目にすると思います。
だったら記述は勉強しなくていいか?となると
60点もの配点がある記述式を全く勉強しないなんてちょっと怖くないですか?
実際私はそれなりの時間を記述の勉強に割きました。
そこで今回は昨年(2024年)の行政書士試験に初挑戦独学で合格した私の記述式の勉強方法を紹介しようと思います。
記述式に悩んでおられる方は参考にしてみてください。
記述式にどう向き合うか
さっそくですが、記述式は例年であれば行政法から1問、民法から2問出題されます。
それぞれ20点ずつ、60点の配点です。
なんで記述式はあてにせず、マークシートだけで180点を目指そうという話になるかというと
得点が高いわりに出題数が少ないんですよね。
3問しかないので、3問とも初めましてみたいな問題が出ないとも限らないんですよ。
なのであてにはできない。
正確にいうと、180点の目標の中に、記述式の点数を予定しにくいという感じです。
マークシートで180点を目指し、足りなかった分を記述式で補えればいいかなと思う人も多いでしょうね。
それでも私は記述式も半分は取りたいなと思っていました。
マークシートで180点を目標にして、記述で30点とれれば、どちらも少し目標に届かなくとも、合計で180点超えられるんじゃないかと。
ただ、前述したように、記述式にあまりに高い点数を期待するわけにもいきません。
なので、半分が目標。
そこで、「それなりに」勉強することにしました。
それなりってどれくらい?
じゃあ「それなり」ってどれくらいなのかというお話ですよね。
私は勉強の主軸を肢別に据えていました。
私の受験生時代の過ごし方は、ほぼ毎日肢別を回すことでした。
この毎日のスケジュールに、記述の勉強を週に何日いれるとかにするのか?
結構悩みましたね。
ただ、記述式といっても範囲は行政法と民法です。
選択式を勉強している知識で記述式が解けたりしないかな?と考えて、ひとまず肢別を回すことを優先しました。
そうしているうちに、模試の時期がやってきます。
実際に記述式を解いてみて思ったこと
 マツモト
マツモト知ってるのに言語化できない…
これなんですよね。
知識としては、例えば行政法なら訴訟法のことを言っていて、結論がどうだというのまではわかる。
でもどう書けばいいのかわからない。
あれこれ書いているうちに時間が過ぎてしまい、さらに焦る。
こういうことが発生しました。
はっきりしたのは、記述式は勉強するというより書く練習をしなきゃいけない。
ということ。
だったら、日々の勉強時間にどのように組み込めばいいのかもつかめてきます。
さっそく記述式の問題集を購入しました。
購入したのは出る順のものにしました。
書く練習をしたかったので、書き込む用のマスがついていることと、肢別が合格革命シリーズだったので解説文が違う感じで新鮮さがあってメリハリがついていいかなと思ったのが選んだ理由です。
私は電子書籍で購入して使っていました。
これを先ほど上で書いたように「それなりに」取り組む方法を考えます。
作文の練習と同じで、しっかり時間をとって勉強するというより、日々の中で習慣のようにした方が良いかなと思いました。
そこで肢別をやる前に30分程度、肢別に飽きたときに1問か2問程度、問題を解くことにしました。
やっているうちに字数制限にも慣れますし、書き方のコツもつかめてきます。
記述式の「書く練習」がマークシート式にも役立った
この勉強方法、やってよかったなというのが、マークシートの点数アップにもつながったことです。
というのも、択一式の問題は選択肢を読みながら正解を考えますが、判断材料がたくさんありますよね。
あやふやな知識でも解けてしまう問題も結構あります。
でも記述式はかなり正確な知識でないと、きちんとした答えは書けません。
今まで模試で解けていた部分も、わかったつもりでいたけど実際はあやふやだったんだと思い知らされることが多かったです。
そういった気づきから、肢別を回すときも意識するようになり、結果としてマークシートの点数アップにもつながりました。
この勉強方法があなたに合うかどうかは、1度模試か過去問を解いてみると判断がつくと思いますので、それからぜひ考えてみてください。
何も準備しないより、準備しておいた方がいいと私は考えます。