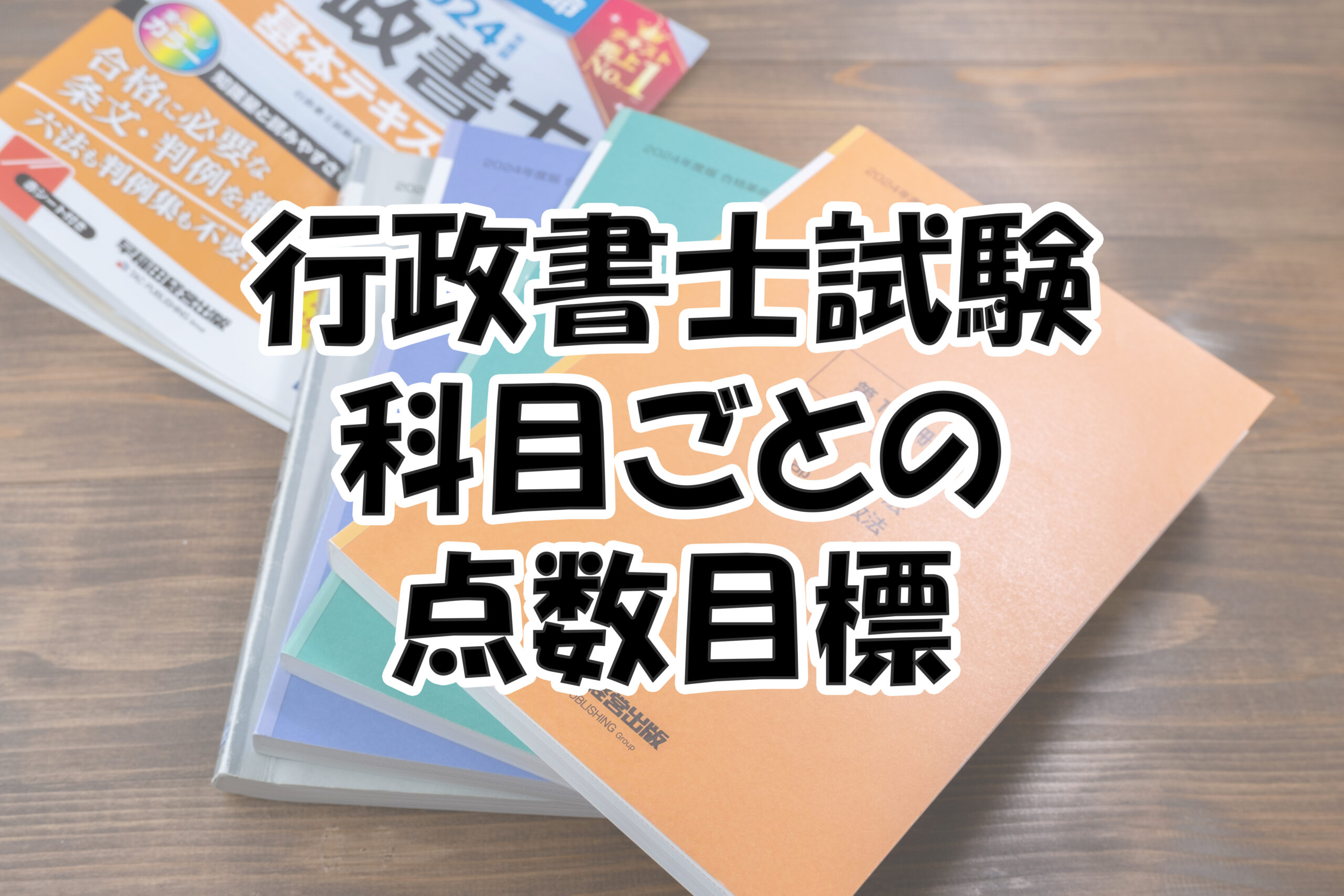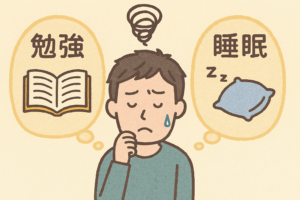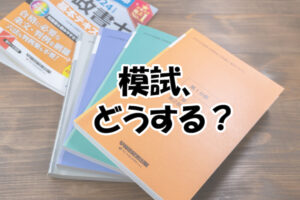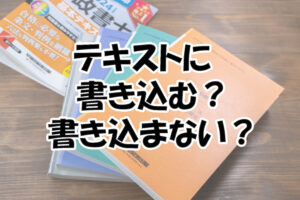こんにちは。行政書士のマツモトです。
本日は行政書士試験について。
行政書士試験にはいくつかの法律、科目があります。
何をどのくらい取ればいいのか、目標設定に困ることや悩むことはないでしょうか?
というのも、それぞれの科目に目標点数がないとどれをどのくらい勉強するかというのも決めづらいですよね。
ただ、これを決めずにただ漠然と勉強していると、かなりアンバランスな時間配分になってしまいかねません。
模試においても、自分がどの科目が弱いのか、到達度はどのくらいなのかというのも把握しづらくなってしまいます。
結果、効率が悪くなってしまうのです。
時間がある人はそれでもいいのかもしれませんが、行政書士試験を受験するのは私と同じく社会人がほとんどですよね。
時間は限られています。
そこで、無駄なく勉強時間を配分するために、本日はどの科目をどのくらい取ればいいのかについて書いていきます。
あくまで受験生時代の私が立てた目標ですので、あなたの得意科目不得意科目に合わせて調整してみてください。本記事は、これが絶対という意味ではなく、目標を立てる参考にしてもらうための記事です。なお、試験科目や配点、形式は変更となる可能性もありますので、最新情報はチェックしておきましょう。
まずは全体の目標を決めよう
まずは全体の目標から決めていきましょう。
もうご存じでしょうが、行政書士試験は若干の上下がある可能性はありますが、180点が合格ラインです。
これを超えないといけないわけですが、マークシートと記述の合計で180点を目指してしまうとかなり厳しいです。
というのも記述は勉強していても全然書けないという事態が起こりかねません。
配点は高いけど3問しか出ないので、それぞれでキーポイントを外してしまうと0点もあり得ます。
なので、理想はマークシートだけで180点以上取っておきたい。
200点を目標にして、結果的に180点超えるようにするというのでもいいでしょう。
ただ目標点数が高すぎるとメンタル的にハードルが上がりすぎてしまうかなと思うので、今回はマークシートだけで180点を目標に設定してみます。
問題は記述式の目標設定ですが、私はざっくり半分取れればいいかなと思っていました。
というのも先ほど書いたように、3問とも初見という可能性もなくはないので、あまり高い目標にして記述の勉強時間を多くとりたくなかったのです。
行政書士試験の科目とそれぞれの配点は?
行政書士試験の科目は大きく分けて2つ。
法令等科目と基礎知識科目です。
この2つにはそれぞれ基準点が設定されていて、これを両方クリアする必要があります。
いわゆる足切りですね。
法令等で記述込み122点、基礎知識で24点が基準点です。
さらに法令等科目は
- 基礎法学
- 憲法
- 行政法
- 民法
- 商法・会社法
の5つがあります。
法令等科目については、五肢択一と多肢選択がありますよね(記述もありますが、先ほども書いたように省きます)
多肢選択については憲法と行政法から出ますが、形式が違うので私は分けて目標設定しました。
それぞれの出題数は
| 科目 | 出題数 | 配点 |
| 基礎法学 | 2 | 8 |
|---|---|---|
| 憲法 | 5 | 20 |
| 行政法 | 19 | 76 |
| 民法 | 9 | 36 |
| 商法・会社法 | 5 | 20 |
| 多肢選択式 | 3(1問につき4つ解答) | 24 |
| 基礎知識 | 14 | 56 |
| 合計 | 240 |
このようになっていて、多肢選択式については例年であれば憲法から1問、行政法から2問出題されます。
形式としては長文が書いてあって、4つの空欄があるので、そこに入る適当な語句を選択肢から選ぶというものになっています。
つまりは12個マークするということですね。それぞれ2点の配点で合計24点となっています。
先ほども書いたように目標は180/240です。
記述に関しての目標については下記の記事をご参照ください。
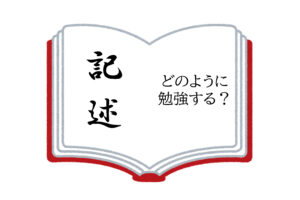
各科目の目標点数とその理由
さて、本題の何を何点取ればいいのかについて書いていきます。
まずいきなりですが、目標点数を表にしましたのでご覧ください。
| 科目 | 目標正答数 | 目標点数 |
| 基礎法学 | 1/2 | 4 |
|---|---|---|
| 憲法 | 3/5 | 12 |
| 行政法 | 17/19 | 68 |
| 民法 | 6/9 | 24 |
| 商法・会社法 | 3/5 | 12 |
| 多肢選択式 | 10/12 | 20 |
| 基礎知識 | 10/14 | 40 |
| 合計 | 180 |
個人的な目標ですが、私の場合は上のように設定しました。
それぞれ理由を書いていきます。
基礎法学
基礎法学は1/2ですね。
なんで半分かというと、基礎法学は模試を解いていても感じたのですが、ほとんどの場合初見であることが多かったんですよね。
基礎法学っていっても結構範囲が広くて、勉強がしづらい分野です。
その割に出題は2問と少ない。
ここにあまり時間を使いすぎるのはタイパが悪いかなというので、私の場合は肢別でやってなかった分は仕方ないかなと割り切ることにしました。
なので、半分取れたらラッキーくらいの気持ちでいましたね。
憲法
憲法については3/5です。
憲法は新しい判例からの出題や知らない判例も出てきます。
が、これは肢別を回しながら気になった判例について調べたり、判例を読んだりしているうちに、最高裁判所の結論ならこうじゃないかなという勘が働くようになります。
なので模試等でもせめて3/5は取りたいなという感じです。
4問としなかったのは、憲法で4問取ろうと思うと憲法の判例問題に割く勉強時間があまりに多くなりすぎるかなと思ったからですね。
憲法の判例問題については下記記事に詳しく書いています。
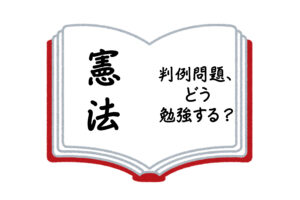
行政法
行政法については17/19です。
本当は満点を目指したいのですが、そうなると地方自治法にかなりの時間を取られてしまいます。
これも先ほどの基礎法学と同じ考えで、肢別の地方自治法で出てこなかったものは仕方ないと割り切りました。
なので、地方自治法である程度落とすかなということで17/19です。
逆に言えば、そのほか行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法では全く落とせないというのが行政法です。
そのくらいの気持ちで勉強しました。
模試で行政法の点数が振るわないうちは、行政書士試験合格はかなり厳しいと自覚していました。
しっかり勉強していれば取れる問題が多いので、逆に落とせないんですよね。
ここは結構プレッシャーかかるけど、「行政」書士試験なんだから、行政法のハードルが高いのは当然なのかなと思いました。
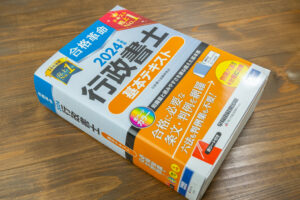
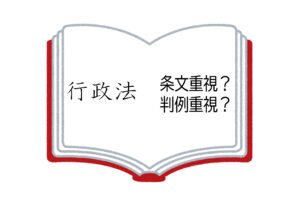
民法
民法は6/9という、ちょっと甘めの目標設定です。
というのも、行政書士試験の民法って結構難しいと思うんですよね。
なので、ここはある程度目標を下げてもいいのかなと考えました。
全体の優先度でいうと、かなり高い科目ではあるのですが、あまり高い目標を設定して模試で落ち込んだりしない方がよいと思います。
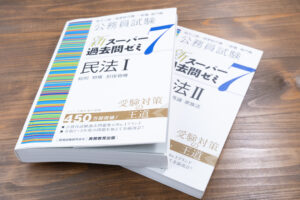
商法・会社法
商法会社法といっても、ほとんどは会社法ですね。
会社法はややこしいです。
組織がいろいろ出てくるし、私が最も苦戦した分野かもしれません。
3/5という設定は、実際は結構厳しくはあると思います。
なので、体感的には憲法くらいの時間的リソースを割いたかなという感じですね。
肢別のページ数でいうと少なめではある科目なのですが、その割に覚えることが多い分野でもあります。
しっかりと組織ごとの違いを把握するのがポイントです。
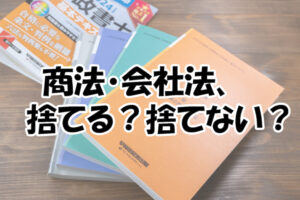
多肢選択式
多肢選択式も対策の立てにくい科目です。
私の勉強方法を簡単に書いておくと、先ほど上でリンクを張った記述式についての記事のなかで紹介している記述式問題集に多肢選択式の問題も掲載されています。
そこで、その問題を肢別の合間にちょこちょこ解いていました。
で、10/12という目標設定はかなり高いようにも見えますが、私の場合は学生時代から国語科目は得意だったんですよね。
そうすると、多肢選択式の問題集をやっているうちに、空欄の前後の流れで正答できるものが結構ありました。
なのでここは10/12は取りたいなと思ったんですよね。
逆に国語科目が苦手な方は、ここは配点が1つの空欄につき2点ですので、その分5肢択一の目標をどこかで1問増やせば8/12の目標でもいいのかなと思います。
基礎知識
基礎知識は10/14です。
これは結構勉強がしづらい科目で多くの受験生が困るところじゃないのかなと思います。
ただ、戸籍法や行政書士法など普通に勉強していれば解ける問題も多く、この辺をしっかりとっていけば10/14は取れるんじゃないのかなと思うんですよね。
また、基礎知識には先ほども書いたように足切りがあるので、低い目標設定だとそれが怖い。
法令等科目の足切りにひっかかるようではそもそも合格点に達するのは難しいので、法令等での足切りは心配しなくていいと思うのですが、基礎知識は違います。
24点が足切りラインですので、最低でも6問はとらなきゃいけないんですよ。
時事問題もあるなかで、14問中6問確実に取れるかといわれると結構怖くないですか?
なので私は10問取りたいという目標設定で取り組みました。
時事問題の対策については下の記事をご参照ください。
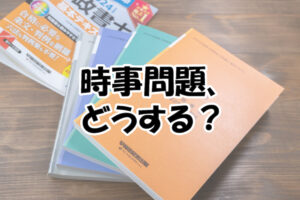
その時はここにもリンクを張ろうと思います。
まとめ:本記事を参考に目標を設定してみてください
さて、今回の記事はいかがでしたでしょうか。
漠然と、科目ごとの目標を立てましょうって書いても何をどうすればよいのか迷ってしまってタイムロスになるかなと思いましたので、参考までに受験生時代の私の目標設定とその理由について書いてきました。
ぜひこれを参考に、自分なりの目標を設定してみてください。
模試を受けるときも、単に結果に一喜一憂するのではなくて、「ここが目標点に達してないな」など的確に分析できるようになり、勉強の時間配分もやりやすくなると思いますよ。
それでは今日はこの辺で。