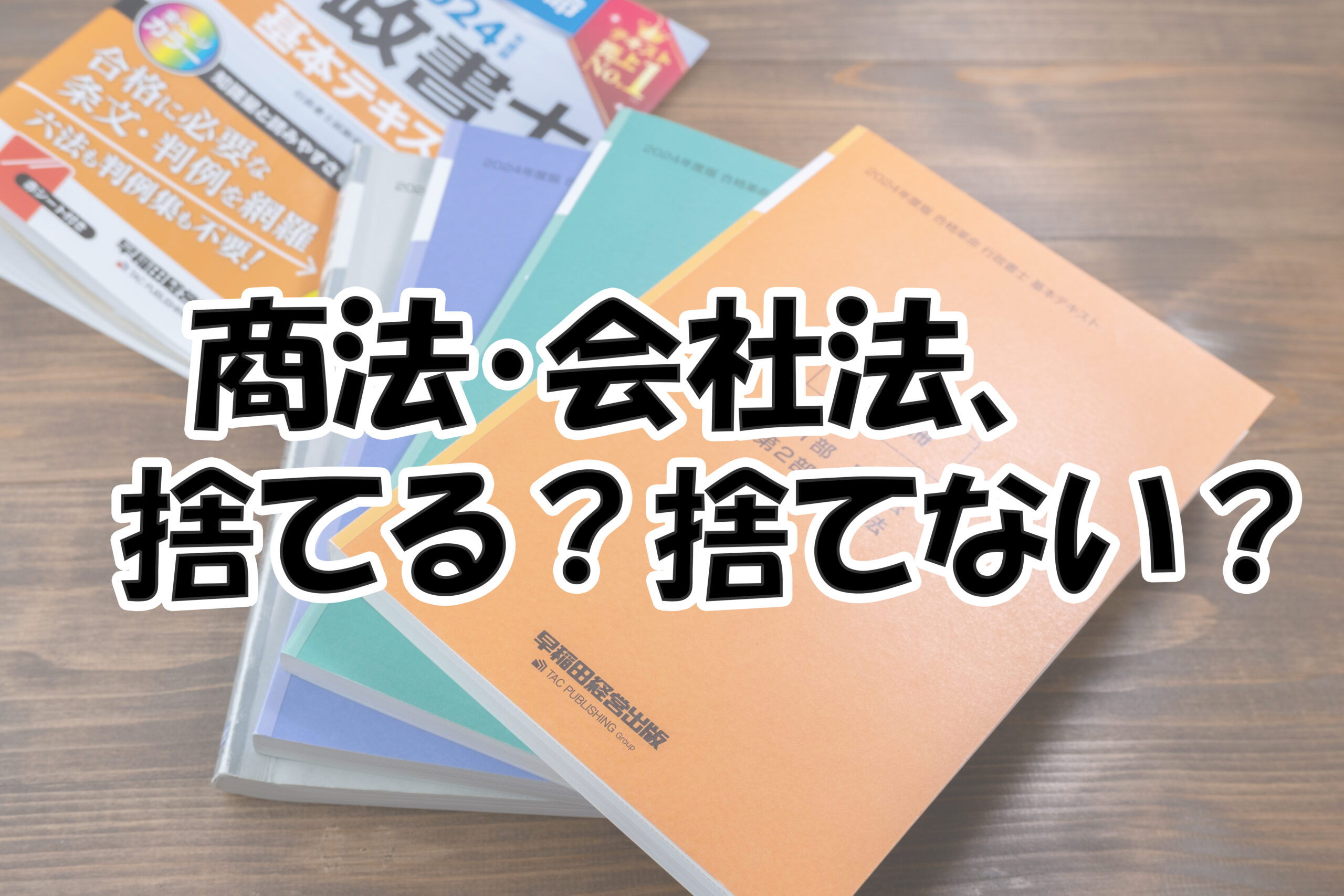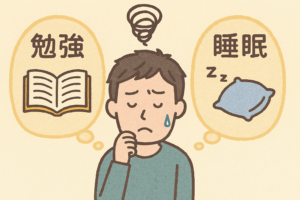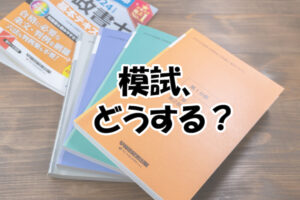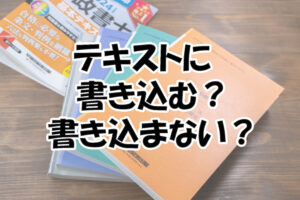こんにちは。行政書士のマツモトです。
本日は行政書士試験の商法会社法について。
商法会社法ってそこまで配点高くないから、どのくらい勉強しておけばいいんだろうって悩むことないですか?
民法と似てるところがあってややこしかったり、会社法においては組織がいろいろありすぎてこれまたわかりづらい。
もういっそのこと捨てちゃおうかなって思っている人も多いのでは?
そこで今回は、昨年(2024年)の行政書士試験に合格した私の場合の商法会社法との向き合い方について書いていきますね。
商法会社法は捨てない
いきなり結論なんですけど、商法会社法を捨てるという選択肢はありませんでした。
もちろん、直前期に勉強を始めていたとしたら、捨ててたと思います。
しかしながら、私が勉強を始めたのは受験する年の1月だったので割と時間があったんですよね。
それに、いくら配点が低いといっても例年であれば、商法から1問、会社法から4問の計5問出題がありますよね。
20点あります。
20点といえば合格を大きく左右します。
時間があるなら商法会社法もある程度勉強しておいた方がよいでしょう。
どのくらい勉強するか
さて、商法会社法も捨てずに勉強するとなると、問題はどのくらい勉強すればよいのか。
ちなみに私の本試験での結果ですが、商法会社法は3/5でした。
これをある程度目安に読んでみてください。
どのくらい勉強すればよいのかについて、私も悩みました。
まずは5問出るうちの何問取りたいか。
模試を解きながら思ったのですが、知らない問題は仕方ないとして、せめて半分以上となる3問は取りたいなと思いました。
また、体感としてですが、模試でも「肢別に書いてあったのにわからない…」といった感じで肢別である程度カバーできる感じがしていました。
なので逆に肢別に書いてなかったら仕方ないくらいで思っていていいのかなと割り切ることにしました。
基本は肢別。あとは組織ごとの整理
やはり、基本は肢別ですね。
肢別を回して、そこで出てくる問題は少なくともわかるようにしておくことで、3問正解を目指そうという感じです。
で、ここでポイントなのですが肢別をただ単に回すんじゃなくて会社法で出てくる組織、例えば監査等委員会設置会社であるとか指名委員会等設置会社であるとかの違いをおさえながら回すのが大事です。
これね、意識していないとスーっと通りすぎていきます。
肢別を回す、このような勉強方法をとる場合、一番怖いのは肢別とお友達になってしまって問題自体を覚えてしまうことです。
ちょっとわかりづらいですかね…
つまり、「あーこの問題ね、ハイハイ、〇」
みたいな感じで肢別の問題自体を覚えてしまって、なんで〇なのか、なんで×なのかを判断しなくなるのが一番よくない。
覚えてしまうのは仕方ないですが、〇の肢であれば、じゃあこの問題は×肢に変えるならどこが変えられるか、×の肢であればどこが誤りなのか、そういったことを考えながら回すことが大事です。
そのうえで、必要な理解が会社法においては組織ごとの違いをおさえることです。
よくでる問題のパターンとして、〇〇会社は△△を置かなければならないとか、公開会社である大会社は…とか、組織の違いをおさえてないと迷う問題が出てきます。
正直、たしかに問題作りやすそうな感じしますよね。
もちろん、組織ばかりではなくて、株主のできることであったり(株主でも何か月前からの株主とか)、資本準備金とか、ややこしい部分も多いのがこの会社法です。
あまり深みにはまって行政法とかが手薄になるのもよくないので
肢別回す→あやふやな箇所は簡単にまとめるなりして資料をさっと作る→次の科目に移る
といったように、肢別を回しながらあやふやな箇所をあぶりだし、かといってそこで何時間も止まらずにさっと資料を作って空き時間に見られるようにするといいですよ。
資料は表でもいいですし、監査等委員会設置会社とか書いてその下に特徴を箇条書きにするとかでもいいと思います。
私の場合は、取締役会とかノートの真ん中に書いて、これを置かなきゃいけない会社を矢印でつなぐとかしてました。
空き時間に見返せるようなものであればなんでもいいかなとは思います。
ノートについては下記記事をご参照ください。

といっても、この商法会社法は受験生でも苦手としている人は多いです。
私が受験生だった時も、SNSで同じ受験生と交流がありましたが、苦手だと言ってる人はよく見かけました。
私も正直、得意ではなかったですね(笑)
ただ、先ほども言ったように商法会社法は満点を取らなくてもいいです。
ほどほどに、それでいて捨てるわけでなく半分以上は取る。
難しいですが、勉強時間の割り振りも重要なポイントですので、バランスを考えながらやっていきましょう。
それでは今日はこの辺で。